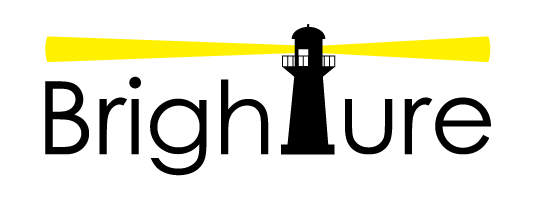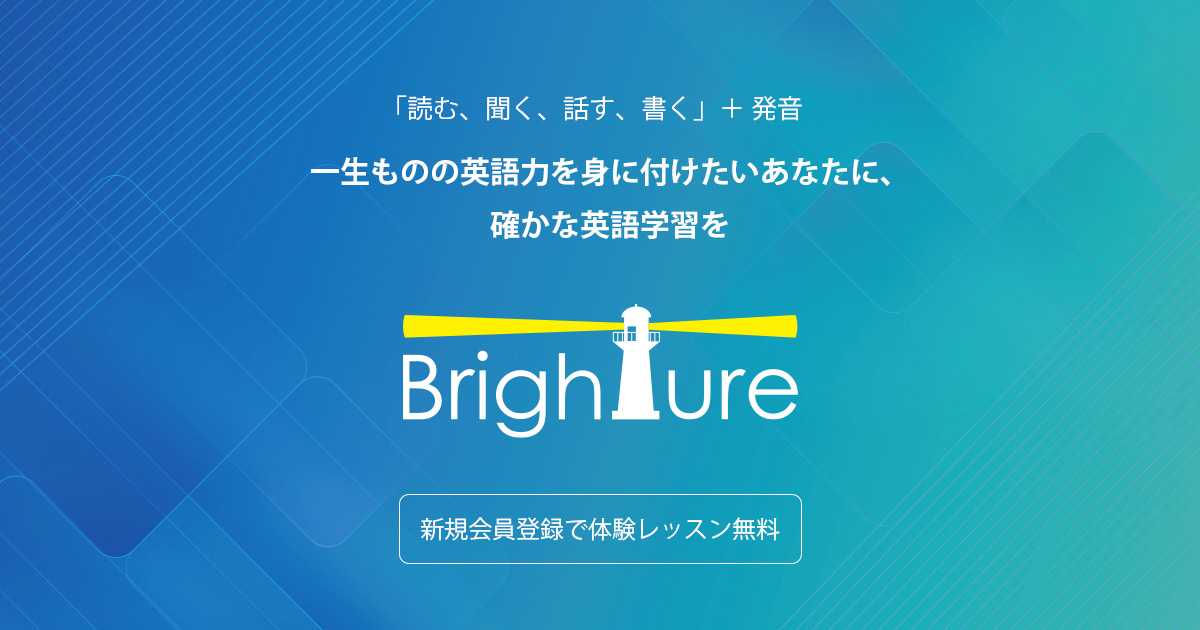22 4月 英語が通じない駐在妻が直面する3つの壁とその対処法
アメリカ駐在が決まった——。
そう聞くと多くの人が「すごいね!」「うらやましい!」と声をかけてくれるかもしれません。
実際、給与や待遇は悪くありません。住居手当もつくし、渡航費用だって会社が負担してくれます。滞在中に英語も覚えられるでしょう。外から見れば、確かに恵まれた立場に見えるかもしれません。
でも、実際にアメリカで生活を始めてみると、多くの人が「見えない壁」にぶつかるんですね。特に、帯同で渡米した妻たちは、その壁に悩み、孤立し、ときに折れそうになります。
本記事では、アメリカ駐在に伴う英語の壁を3つに分けてご紹介します。そしてその壁をどう越えるか、そのヒントもお伝えできればと思います。
駐在妻が直面する英語の「発音」の壁
まず最初にぶつかるのが、「言っているのに通じない」という「発音の壁」です。
多くの方が英語を学校で学んできて、それなりの語彙も文法も知っています。ところが、「Do you have hot tea?」など、簡単なことを訊いているだけなのに、コンビニや喫茶店の店員に「Huh?」と聞き返されたりします。僕なんか「map」と言っているのに「mop?」と聞き返されて心が折れそうになったことがあります。
店員は決してエリートではありません。言ってみればごく普通の人ですが、そういう一般人にごく簡単な単語すら通じないという事実が、想像以上に自尊心を削るんですね。
問題は母音の発音にあります。日本語の母音は基本的に「あ・い・う・え・お」の5種類しかありませんが、英語には少なくとも14種類以上の母音があるんですね。そんなわけで、驚くほど簡単な単語が通じなかったりします。
saw と sew、bug と bag、map と mop など、まあまあ通じないんですね。また Caffè Latte とかも通じない単語の代表格ではないかと思います。
多くの人が英単語をカタカナで最初に覚えてしまっているという「初期設定のズレ」も影響しています。これは本当に困りもので、カフェラテが Caffe Latte なのか Cafe Ratte なのかわからなかったりするんですよね。僕も「kerosene(灯油)」を「カロシン」として覚えていたために、通じなかったことがありました。
こういった「通じない体験」が積み重なると、話すのがどうも億劫になっていくんですね。地味にしんどいです。
学校や病院で英語が通じない「生活」の壁
次に待ち受けているのは、「生活の根幹に関わる」場面での壁です。
特に深刻なのが、病院と学校なんですね。
体調が悪いときに英語で予約を取り、症状を説明し、医師の話を理解する——これは想像以上にハードルが高いのです。ただでさえハードルが高いのに、具合の悪さが手伝って、判断力も言語力も落ちてしまう。
子どもを連れて病院に行く場合には、さらにプレッシャーがかかります。「この症状をどう説明すればいいんだろう」「もし重大なことを見逃してしまったら……?」という不安。
学校での先生との面談も同様です。たった15分〜20分の短い面談の中で、先生の話す英語を聞き取り、必要な質問をし、自分の考えを伝える。それができないと、「親としてちゃんと話せなかった」という自責の念が残ったりします。
そしてこれらは、帯同している妻たちが対応することが多い場面なんですね。
夫は日々職場で英語を使っているため、ある程度「慣れ」ていくことができます。でも、奥さまたちは日常の中に英語の強制力が少なく、孤独に壁と向き合わなければならない——ここに、非常に大きなギャップがあります。
関連記事:英語での診察は、カンニング帳で乗り切ろう! (歯医者編①:飛び込み診察)
関連記事:英語での診察は、カンニング帳で乗り切ろう!(検査編)
英語での雑談ができない「つながり」の壁
そして最後に立ちはだかるのが、現地の人との「つながり」を阻む壁です。
最初の壁(発音)や二番目の壁(医療・学校)は、ある意味「技術的」なものであり、練習すれば改善する余地があります。でも、この「雑談」と「人間関係の距離感」は、文化の問題でもあり、なかなか難しいんですね。
まず、日本とアメリカでは人間関係の築き方がまるで違います。日本は、距離を少しずつ縮めていく文化ですが、アメリカは、初対面からフレンドリーです。でも、実は必ずしも「深く」なるわけではないんですね。相手が笑顔だからといって、親密とは限らない。関係がなかなか深まらない。こうした文化の違いに、最初は誰もが戸惑います。
そしてもう一つの問題は、「そもそも接点がない」ことです。アメリカでは、偶然の出会いから自然に友達になるということは少なく、何かしら目的を持って自分から行動しない限り、関係は始まりません。
さらに、共通の話題が見つからないという壁もあります。アメリカのテレビ、スポーツ、政治……どれもピンと来ない中で話題を振られても、反応できない。雑談力以前に、話す内容がない状態だったりしますよね。
そして極め付けが、英語力そのものです。スラングやジョーク、早口の言い回しがわからず、笑うタイミングさえつかめない。結果として、壁の花となってニヤニヤしているしかなく、自尊心を削られます。本当にしんどいんですよね。
英語ができない不安をどう乗り越えるか
では、こうした3つの壁をどう乗り越えていけばいいのでしょうか?
僕が強くお勧めしたいのが、習い事を始めることです。英語を目的として学ぶのではなく、英語を「手段」として何かをすることで、自然なコミュニケーションが生まれます。
たとえば、料理教室、ヨガ、ボランティア活動、英語を学ぶアメリカ人との言語交換など、何でもいいと思うんですね。「今日はどうだった?」と聞ける共通の文脈があることで、雑談のハードルは一気に下がります。
また、発音については、「初期設定のズレ」をリセットする意識で取り組むことが大切です。自分の声を録音して聞き直す、AI を活用した発音フィードバックツールを使うなど、いまは自宅でできる練習法がたくさんあります。
Brightureのオンラインレッスンは駐在妻の英語学習にも効果的
もし、こうした悩みに向き合いながら「でも何から始めたらいいかわからない」と感じている方がいたら、Brighture(ブライチャー)をぜひ覗いてみてください。
Brighture では、駐在員やそのご家族のために、
- 発音矯正や母音トレーニング
- 実生活に即した会話練習
- 雑談力を高めるグループレッスン
などを提供しています。
オンラインなので、アメリカ国内のどこにいても受講可能ですし、英語力の「基礎」だけでなく、「心の折れやすい部分」にも寄り添うのが、Brighture のスタイルです。
駐在生活を「ただ耐える時間」にしないために——。ご自身のペースで、まずは一歩踏み出してみませんか?
▶ 詳細はこちらからどうぞ!