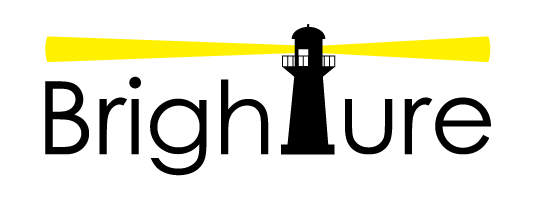10 4月 【英語エッセイ】The Sound Inside the Closet(クローゼットの中で)
この記事は、Brighture の講師が書いた英語エッセイです。
On my 25th birthday, I randomly came out for the first time to my then newfound friend, Jill. Finally, I felt like I had freed myself from being in the closet. It was an unexpected dinner invite, because she pitied me for not celebrating. It turned out to be a life-changing moment, the beginning of me finally knowing myself more for who I am. Before then, I didn’t fully comprehend what I was (or at least at that point I still didn’t want to accept the truth).
25歳の誕生日、当時友達になりたての Jill に、不意に初めてカミングアウトしました。ようやく、自分の殻から解放されたような気がしました。
その日、祝ってもらえない私を哀れんで、彼女がディナーに誘ってくれたんです。それが人生を変える瞬間になり、自分が何者であるかをもっと知るためのきっかけとなりました。
それまでは、自分が何であるかを完全には理解していませんでした(あるいは、少なくともその時点では、私はまだ真実を受け入れたくはなかったのです)。
Don’t get me wrong, I did understand that my feelings and preferences screamed gay. There it was, my attraction to other boys: the itchy feeling in my toes every time my best friend, Adrian, would have his arm over my shoulder, the buzz of my seatmate’s thigh brushing against mine in music class. I was 12, a shy kid whose favorite color was blue, but lights up when he sees Pink Ranger and Cardcaptor Sakura.
誤解を恐れずに言うと、私は自分の感情や嗜好がゲイであることは理解していました。
親友の Adrian が私の肩に腕を回すたびに足の指がむずむずしたり、音楽の授業で隣の席の人の太ももが私の太ももに触れるとざわざわしました。男の子に魅力を感じていました。
12歳の私が好きな色は青でしたが、ピンクレンジャーやカードキャプターさくらを見ると元気になるような、内気な子供でした。
I thought being gay was a choice. I also thought that taking that path would mean my friends would think I was a perv. I would probably be ostracized at Sunday school. And if Mom and Dad found out? My mind could not fathom what might happen then. That was how I defined being gay: a problem. I thought that there was no happiness to be found in being gay. “It’s just a phase,” I told myself. I took a detour and shut myself in the closet, a decision I made since time immemorial.
ゲイであることは選択肢の一つだと思っていました。その道に進むと、友達に変態だと思われるとも考えていました。
日曜学校で仲間はずれにされるかもしれない。もし、パパとママにバレたら?
一体どんなことになるのか、想像もつきませんでした。そうやって、ゲイであることを「問題」だと定義していました。ゲイであることに幸せは見いだせないと思っていました。「ただの変化の時期」だと自分に言い聞かせました。私は現実に向き合わず、殻に閉じこもることにしました。
I thought that curling up inside the realm I created, however dark, would give me solace. That I could simply traipse through streets hiding behind button-up shirts, a clean haircut, and straight A’s; the boy everyone I loved wanted. By choosing to be straight, life would be easier. Except that, because I was keeping so many things from everyone, the anxiety was always at bay, pouncing at the most critical times. I was always so cautious not to be accidentally outed through my actions. This meant that I had to be mindful of the way I walk, because in disapproving eyes, one sway of the hip could give it all away. Every move I make and word I say must be precise, rehearsed, ready to be performed in front of an audience. Hands in the pocket, deep voice, it’s always an act. It was exhausting.
自分の世界に閉じこもれば、どんなに暗くても、癒しになると思っていました。ピシッとしたシャツ、清潔なヘアスタイル、成績優秀者を隠れ蓑にして振る舞うだけで、誰からも愛される少年になれると。
ストレートでいることを選択すれば、人生はもっと楽になるはずでした。
ただ、私は多くのことを隠していたので、常に不安がつきまとい、大事な場面で襲いかかってきました。自分の行動でうっかりバレてしまわないように、いつも気を遣っていました。だから、歩き方にも気を使っていました。嫌な顔をされて動揺したら、腰の動きひとつでバレてしまいます。
私の動きや言葉は、観客の前で披露するために、すべて正確で、リハーサルされたものでなければなりませんでした。ポケットに手を入れ、深い声を出す。それは常に演技なんです。疲れちゃいます。
I remember that if there’s one place I dreaded the most growing up, it was the dinner table at family reunions. There was the nosy aunt with her unending questions, the religious conversations, and the unsolicited opinions and advice from people who only showed up once in a blue moon yet they suddenly felt that it was their job to be concerned about your life choices, as if feeding on your fears and uneasiness. The main course that they wanted to dig in was my long luscious curly hair. “Why did you grow it that long?” “When are you going to get a haircut?” “It’s cool but you look like a girl. It doesn’t suit you.”
子供の頃、一番苦手だった場所は、家族で囲む食卓でした。
おせっかいなおばさんの取り留めのない質問や宗教の話。滅多に顔を出さないのに、「あなたの人生を心配するのが私の役目」だと感じている人からの迷惑な意見やアドバイス。まるで自分の恐怖や不安を、私にアドバイスすることで誤魔化そうとしているようでした。そして、その人たちが食いついたのは、私の長い巻き毛でした。「どうしてそんなに伸ばしてるの?」「いつ髪を切るの?」「かっこいいけど、女の子みたい。似合わないよ」
There’s not enough training and acting skills that would make someone ready to be placed in that position. I was just trying to enjoy my meal but I always felt ambushed, shaken, and crushed.
私には、そういうことに対応できる鍛錬や演技力が足りませんでした。ただ食事を楽しみたいだけなのに、いつも攻撃され、揺さぶられ、押しつぶされそうになりました。
It’s not an uncommon scene for me. For as long as I could remember, it was instilled in me that being gay is wrong. Brought up in a family of devout fundamentalists, it’s very common for me to listen to the stories of Sodom and Gomorra and how it is a sin to be gay, that God only made an Adam and an Eve, and the Caitlins and the Elliots should not exist. I grew up believing that choosing to be queer would only make you end up in the burning pits of hell. And, while living, you become a laughingstock, a walking variety show, deprived of love and respect.
でもそれは私にとって珍しくもない光景です。物心ついたときから、ゲイであることはいけないことだと植えつけられていました。
信仰心の厚い原理主義者の家庭で育ったので、ソドムとゴモラの話や、ゲイであることがいかに罪であるか。神はアダムとイブを作っただけで、ケイトリンやエリオットは存在すべきではない、という話を聞くのはごく普通のことでした。私は、同性愛者であることを選択すると、灼熱地獄に行き着くだけだと信じて育ちました。そして生きてるだけで、笑いものにされ、歩くバラエティーショーにされ、愛と尊敬を奪われるのです。
And I didn’t want to be like that at all.
そんなふうには、なりたくなかったです。
It has been more than six years since I first spoke my truth to Jill, currently one of my best friends. It hasn’t even been that long but numerous defining moments already altered the course of my life. Many have shown me support and love and it is an inexplicable feeling to be free, yet I still have not gathered enough strength to come out to my family. As most of them say, do it when you’re ready. But the truth is, I don’t think I will ever be ready. The thought of disappointing my family and the risk of losing them always extinguishes my courage. Perhaps, in time, the sound inside the closet will become too much, and there’s nothing to do but to let it all out.
親友の一人である Jill に初めて真実を語ってから、すでに6年になります。まだそれほど時間は経っていませんが、すでに数々の決定的な瞬間が私の人生を変えてきました。
多くの人が応援し、愛情を注いでくれて、自由になれたという言いようのない喜びがあります。でもまだ家族にカミングアウトするほどの力は蓄えていません。多くの人が言うように、その時がきたらやればいいと思っています。
しかし、実際のところ、カミングアウトする日は訪れないと思うのです。家族を失望させ、失うかもしれないという思いが、いつも私の勇気を奪います。おそらく、やがて自分の内なる声が大きくなりすぎて、すべてを吐き出すしかないのだと思います。